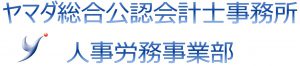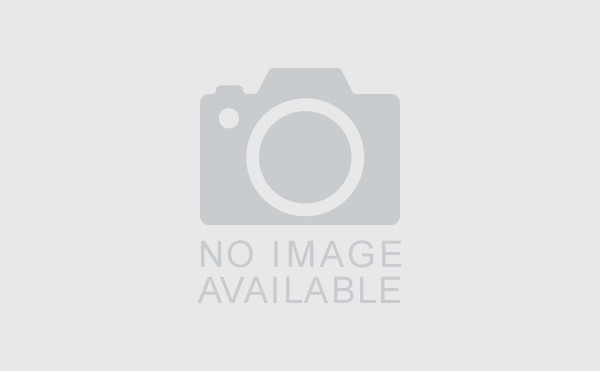無効な36協定下の違反めだつ 押印廃止が影響し 上野労基署
東京・上野労働基準監督署(津田太郎署長)は、有効な36協定がないまま時間外・休日労働を行わせている事業場の増加を受け、監督指導や集団指導を積極化している。届出書と協定書を兼ねる場合、協定届に過半数代表の押印または署名が必要だが、届出書の押印・署名廃止や電子申請の普及に伴い押印をせず、実質的に“協定書なし”となっている事業場がみられている。ほかにも、休日労働の始業・終業時刻を「とりあえず平日の定時と同じにする」など、実態にそぐわない記載をしているケースもめだつ。同労基署の担当者は「36協定が形骸化している」と危機感を示す。
コメント:前提として、法律では一日8時間、一週間40時間を超える労働を、「それ以上働かないようにして下さいね。」と、基本的に制限しています。
ただ、そうはいっても忙しい時はどの会社もあるはずですし、どうしても一日8時間、1週間40時間のルールを守ることができないときはあります。
36協定は、簡単に言うと、そういったどうしても一日8時間、一週間40時間を超えてしまう場合に、どれだけ残業できるのかなどの残業に関する取り決めを会社と従業員で話し合って書面にしたものです。
そうすることで、時限的にですが、一日8時間、一週間40時間を超えて働くことがあっても法律違反としないという扱いを受けることができます。
従来は、36協定の作成にあたり、従業員の押印が必要だったのですが、コロナ以降押印が不要となり、その代わり署名で済むようになりました。
また、今までは36協定を作ったら、紙で労働基準監督署に提出していたのですが、パソコンで36協定を申請することができるようにもなりました。
記事の通り、コロナ以降の変更で、作成がし易くなったのはいいですが、36協定が、形だけのものになっていることが問題になっているようです。
36協定で大切なことは、どれだけ残業できるのかなどの残業に関する取り決めを会社と従業員で話し合うことだと理解していますが、実務をしていると、36協定で一番大切な話し合いをしなくとも、簡単に申請できてしまうな。と思うことがあったりもします。
今後は当事者が法律に対する意識をより高めるのも大事ですが、もっと36協定の趣旨を担保できるような制度も並行して整備されればいいですね。
【出典】
記事タイトル:無効な36協定下の違反めだつ 押印廃止が影響し 上野労基署
機関名:労働新聞社
掲載年月日:令和7年7月31日
Webサイト名:労働新聞社HP
URL:無効な36協定下の違反めだつ 押印廃止が影響し 上野労基署|労働新聞 ニュース|労働新聞社
参照年月日:2025年8月7日